| タイトル:スペーシャリスト会報 Vol.206 | 発行日時:2024年2月15日 |
|
┏ Magazine from Spatialist Club ━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 2024年2月15日(木) ◇ スペーシャリスト メールマガジン ◇ vol.206 発行元:スペーシャリストMM事務局 https://spatialist.sakura.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ *SPの会事務局からのお知らせ ★ ★★ *ニュースラウンジ 橘 菊生 *リレーエッセイ<空間連携> 清成研二 *新入会員の 金田英治、加城文彦 *空間情報関連/書籍紹介 安藤港増 *企画委員会議事録(抄) 遠藤拓郎 *日本測量協会からのお知らせ 遠藤拓郎 *編集後記 大山容一(添付あり) ■SPの会事務局からのお知らせ( ★ ★★ 企画委員会議事録(抄)をご参照 ) ★ SPの会企画委員会に設立する 「働きながら博士号取得をめざす人のための相談コーナー」のお知らせ 測量・地理空間情報技術者で将来、学位(博士号)を取得したいと考えている人 などを対象に、博士号取得に向けて本格的な始動をするまでに準備すべきことや 取得までのプロセス、取得方法(課程博士か論文博士か)等々について、個別に 相談できるコーナーを本年4月より設置します。アドバイザーはSPの会最高顧問 の瀬戸島政博氏が担当します。詳細は3月号・4月号のMM誌で紹介します。 ★★ 第1回 測量技術者のための人財育成懇談会(2024年1月)議事概要 日時:2024年1月30日(火)15:00~17:00 場所:日本測量協会 第2会議室、WEB 1.メンバーの自己紹介 2.本懇談会設立の背景と趣旨 3.本懇談会の運用について 4.検討する命題と開催時期 ・取り上げるテーマについて(メンバーからの意見) 「会社のマネジメントを担うための人材育成」、「後継者不足に対する人材育成」 「外国人や障害のある人を働き手とする人材育成」などの意見が挙がる。 5.テーマ:現状認識とその共有(※フリートーク抜粋) 「測量界全体が高齢化」、「業界の魅力発信が足りていない」、「外国人向け の測量訓練が必要である」、「若い世代を取り込むためには、若い人に合わせ たPR方法が必要ではないか」、「体験会、フェアなど測量に触れる機会の創出 が必要である」、「小学生や中学生といったより若い層に出前講座等を実施する」、 「入社後に、測量士、測量士補の資格を取得させる支援システムつくり」、 「測量士・測量士補の試験は受験資格に制約がない、そこで小・中学生を対象と した受験対策講座を行う→私たちも足元から見直す」など。 次回予定:2024年3月21日(木)15:00~17:00(予定)第2回人財育成懇談会 ディスカッションテーマ:「現状認識とその共有」 ■ニュースラウンジ 新型コロナウイルス感染症は徐々に収まり、昨年5月に5類へ移行されました。各種 イベントなどのオンサイト開催なども普通に行われるようになり、コロナ前の平穏な 状況に戻りつつあると思っていた矢先の元旦に能登半島地震が起きました。震源地は 石川県の能登地方でマグニチュードは7.6に達し志賀町や輪島市では最大震源7を記録し、 新潟や富山、福井でも震度5以上の揺れとなりました。私は山形の上山におりましたが、 そこでもかなり長い時間揺れが続きました。次いで5m級の津波が襲ってくるという大津 波警報が出されました。 弊社のデータ処理センターが新潟市内にあり、安否確認の情報が徐々に届く中、 市内に設置されていたライブカメラで状況を確認していました。今回の地震は規模が 大きいことに加え、津波の危険があったため、現地にいた職員は急遽避難を余儀なく されました。事後のブリーフィングで、このような状況で当事者に安否確認の報告 等々を求めるのは無理があること、安否確認のシステムはあるがその先の対策が全く 不十分であることが認識されました。発災からひと月が経過して、様々な調査、分析 結果が出始めています。しかしながらインフラの復旧はまだ完了しておらず、復興に ついては非常に長い時間が必要であると思います。SP会や地理空間情報技術者がどの ように寄与できるのか改めて考える必要があるのではないかと思っています。 前回ニュースラウンジの記事を担当させていただいたのが2023年の3月で、4月に 作業規程の準則が改訂され、写真測量における直接定位の解析にもTightly Coupled 解法が使用可能となりました。先日たまたま処理ソフトウエアのマニュアルを見る 機会がありました。当然ながらTightly Coupled解法が標準で、品質管理に関しても システム化されており、機能や方法などについても丁寧に説明されていました。 ただし、今のソフトウエアから入った人たちは、それぞれの意味を理解するのが 逆に難しいのではないかと思います。パラメータの設定やデータの取捨選択などは かなり自動化されており、経験をもとに試行錯誤でやっていたことがソフトウエア にお任せ状態となっています。ソフトウエアの性能が上がり、良好な解が得られる ようになることはありがたいことですが、本質的なところを理解しておくことがよ り重要になると思います。このためには技術に関する教育の重要性を非常に感じて います。 ( 橘 菊生:株式会社パスコ ) 〇令和6年3月号の担当は、住田英二さんです ■リレーエッセイ<空間連携> 朝日航洋(株)の白井直樹さんよりバトンを受け継ぎました、朝日航洋(株)清成 と申します。1996年に当社に入社して以来、GISエンジンやGISアプリケーションの開 発に携わってきました。今面白いと感じているITは生成AIで、おおよそ1年前から騒 がれ始めたChatGPTの可能性に気分が高揚しています。昨年末に青山学院大学古橋教 授の講演を聴く機会があり、教授も学生もChatGPTは手放せないツールになっている と伺って、学の世界ではそんなに浸透しているんだと驚きました。 早速無料版を試してみたところ、例えば「BBOXの座標をCSV形式で指定する入力ボ ックスがあり、実行ボタンを押すと地理院地図上にBBOXのポリゴンが半透明で表示 されるWebマップのHTMLを作って」と頼んだら、ものの数秒で目的のコード(しかも 丁寧なコード)を返してくれました。(ついでに「東京都のBBOXの座標をCSV形式で 教えて」と依頼し、出力されたCSVを先の入力ボックスにペーストして、動きも確認 できました) それからというもの、「空間情報技術って若者にとってどんな魅力があるんだろう」 とか、夜な夜な思いついたことをChatGPTに聞いてみて、なるほどと思ったり、ほんと にそうか?と感じたりして楽しんでいます。同じ質問をしても違う答えが返ってきた り、間違ったことを平気で正解のように答えたり、多くの変な癖がありますが、 そこはまた愛嬌ある感じがしています。 GISは仕様や操作を覚えるのが大変で、数多くのデータをどう組み合わせ、どう解析 して目的の主題図を作成するか検討するのにも骨が折れます。新たなアイデアを思い ついてもそれを形にするまでのハードルが高く、あきらめてしまうユーザーも多いの ではないでしょうか。生成AIにこの分野でどんどん力をつけてもらって、なんでも相 談にのってくれる有識者と話す感じでAIと会話を重ね、目的の主題図や空間解析結果 がさっと表示される(正しいことが望ましいですが)、そんなGISがあると、ユーザ ーが楽しくリテラシーを高めることができ、結果、空間情報の活用が広がり、市場が より活性化するのではないかと妄想しています。今後この分野の生成AIに関わってい き、微力ながらもその性能向上に貢献したいと思っています。 読んでいただきありがとうございました。次は当社の横田宏行さんにバトンを繋ぎ ます! (清成研二:朝日航洋株式会社) 〇令和6年3月号の担当は、横田宏行さんです ■新入会員のページ 国際航業の加城文彦(かしろふみひこ)と申します。空間情報総括監理技術者試験に何 度も跳ね返されてきましたが、ようやくSPの会に参加させていただくことができました。 私の専門分野は、市町村の固定資産税に関するGIS及びデータ構築並びに評価支援で すが、入社時はトランシットを担いで山々を渡り歩いていました。それから、道路台帳、 上水道台帳、統合型GISなども経験しながら今日に至っております。これら業務を円滑に 推進するには、地理空間情報技術者として、お客様へ提供するサービス価値を高めるこ と、それを実現する手段として、ポートフォリオ、プログラム、そしてプロジェクトマ ネジメントを身に付け、常に変化する環境に柔軟に対応していくことが重要であると考 えております。 私は、PMI日本支部にも所属しており、地理空間情報分野以外のプロジェクト等に関す る知見を日々のプロジェクトに取り入れながら、現場で奮闘しています。 今後は、SPの会の皆様の地理空間情報技術に関する高度な知見に触れさせていただき ながら、少しでも皆様に近づけるよう研鑽を積んでまいります。 今後ともよろしくお願い致します。 (加城文彦:国際航業株式会社) この度、SP会に入会させていただきました、東日本総合計画株式会社の金田(かなだ) と申します。1998年より25年、実測全般に携わっております。専門分野は、用地測量・ 地籍調査・土地区画整理など「土地の境界」に係る測量です。 そこで一番苦労するのは、地権者との「境界立会」であり、地権者双方の合意を得る ために、多くの手間と時間を要します。将来の展望として、点群データ等を活用して境 界を含めた現地状況を再現したデジタルツインを作成し、自宅に居ながらリモートにて VRゴーグルで簡単に確認できるような「リモート境界確認」が実現して、主流になれば 良いと考えております。 空間情報を活用して、課題解決の実現に向け能動的に活動していきたいと思います。 どうぞ宜しくお願いいたします。 (金田英治:東日本総合計画株式会社) 〇令和6年3月号の担当は、江藤稚佳子さん、江川真史さんです ■空間情報関連便利グッズ/書籍の紹介 等 防災アプリの決定版 【特務機関NERV(ネルフ)防災】 このたびの令和6年能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 発災をうけて、防災対策を見直された方も多いことと思います。災害大国の我が国 では、防災意識も高く、皆様もすでに何かしらの防災アプリをインストールしている ことと思いますが、数ある防災アプリの中でもわたしが最もおすすめするアプリ【特 務機関NERV(ネルフ)防災】の紹介です。 https://apps.apple.com/jp/app/%E7%89%B9%E5%8B%99%E6%A9%9F%E9%96%A2nerv %E9%98%B2%E7%81%BD/id1472338480 「特務機関NERV(ネルフ)ってあの国民的アニメ『エヴァンゲリオン』のNERV(ネル フ)?」という声が聞こえてきそうですが、そうですあのNERV(ネルフ)です。開 発会社の名前もゲヒルン株式会社ですから相当のこだわりを感じます。 (『エヴァンゲリオン』シリーズの著作権者である株式会社カラーの許諾を取った上 で名称を使用しているということです。) 【特務機関NERV(ネルフ)防災】というアプリ名称から「ゲーム? あやしいアプ リ? いざという時につかえるの?」といった印象を受けるかもしれませんが中身は 国内屈指の防災アプリです。地震速報をはじめとした災害情報だけでなく、日々の天 気予報機能も有しており普段使いにも良いアプリです。また、ウィジェット機能にも 対応しており、ホーム画面に常駐させることもできるのも大きな魅力です。 今回の能登半島地震は、X(旧Twitter)に課金及び報酬システムが導入されたとい うこともあり、閲覧数目当てのデマがSNS上にあふれ、社会問題にもなりました。自 分で情報の取捨選択ができればいいのですが、なかなか難しく、やはり信頼できる 情報源を確保しておきたいものです。 これを機会に、防災の一環として、アプリの導入を検討してみてはいかがでしょうか。 (安藤 港増:CSGコンサルタント株式会社) 〇令和6年3月号の担当は、山田秀之さんです ■企画委員会議事録(抄) ( ★★ ★ は 本メルマガ冒頭をご参照) 令和5年度 第2回「スペーシャリストの会」企画委員会(令和6年1月)議事録 日時:令和6年1月19日(金)13:30~16:00 場所:日本測量協会第1会議室、WEB (1) 報告事項 ①支部長交代について(中四国支部) 中四国支部の支部長が越智(荒谷建設コンサルタント)さんに交代となった。 ②各支部活動報告 ③横断的な研究会・懇談会キックオフミーティング ・人財育成懇談会は、第1回懇談会を1月30日(火)15時~17時に開催する。★★ ・最新技術動向の研究会は、近々第1回研究会開催に向けて準備中である。 ・研究会・懇談会のメンバーが確定した。今後も申し出があれば随時入会可能である。 (2) 討議事項・要請事項 ①月刊「測量」スペーシャリストの会コーナーの執筆毎号の確認(第33弾) ②令和6年度KIT空間情報セミナーについて KIT空間情報セミナーは例年5回だが、今年は3回の開催となる。第1回セミナーは 鵜飼が担当する。第2回と3回の担当者は各支部で持ち帰り、候補者を検討する。 ③2024年イノベーション大会SPの会セッションについて ・プログラム案について、企画委員会で検討する。大ホールは講演プログラムを 中心に、多目的ホールは、例年通り、懇親会、ポスター展示、ギャラリー1は パネルディスカッションも含めて自由に、ギャラリー2は講演者等控室としての 使用を予定している。 →今月中に企画委員各自、テーマ案を1つ、2つ、事務局に提出する。それをもと に方向性を決めていく。 ④令和6年度空間情報未来会議について ・大会実行委員会で、開催日時、特別講演者、SPの会発表テーマ、タイムスケ ジュール等について素案を作成し、企画委員会で承認を得る。 ⑤その他 ・(仮称)働きながら博士号取得をめざす人のための相談コーナー(キャリア相談室) について★ →まず第1弾として、博士号を取得したい意識を持つ人の相談室を開設する。 まだキャリア不足でためらっている人たちの後押しをしたい。 ・土木学会 共催について →土木学会に繋がりのあるメンバーについて、引き続き検討する。 ・メルマガのリレーエッセイについて →外部に知り合いがいないため、同じ会社内で回ってしまうことを解消するため、 次にバトンを回す相手に困ったら、早めに支部長に相談するというルールにする。 以 上 ■日本測量協会からのお知らせ ◇転職・退職・死亡等により、氏名・所属・連絡先(メールアドレス)の 変更が生じたSPの会会員の方へ。 変更後の内容をご本人または関係者の方から日本測量協会にお知らせください。 SPの会MM誌の配信やお知らせ等の連絡に支障が出ないようお願いいたします。 届け出様式は以下の場所にあります。 https://www.jsurvey.jp/gissv/youshiki.htm 様式2 空間情報総括監理技術者 登録事項変更届出 メールまたはFAXまたは郵送でお知らせください。 連絡先は以下の通りです。 メール:geoinfor@jsurvey.jp FAX : 03-5684-3366 〒112-0002 東京都文京区小石川1-5-1 パークコート文京小石川 ザ タワー 5 階 公益社団法人日本測量協会 測量継続教育センター 測量技術教育部 宛 ◇空間情報技術事例報告集の報告文募集 ☆応募締め切り:随時(投稿報告文が到着次第、速やかに査読) ☆掲載可となれば、日本測量協会ホームページ上の[測量情報館]に掲載。 技術事例報告集では、新規性や独創性という視点とは別に、 (1)創意工夫性(何らかの創意工夫による業務改善への貢献など) (2)実用性(実務への応用性や実際に業務等に 適用していく際の実用性など) (3)信頼性(技術事例報告の内容やその結果に対して、信頼性や実証性など) (4)今後の展開性(空間情報技術領域の中で、他技術領域への新たな展開や応用の 可能性、他技術との融合性や融合利用の可能性などを含めて今後の展開性) という視点から査読し、技術事例報告として採用致します。奮って、投稿ください。 詳しくは、https://jsurvey.jp/kuukanhoukoku.pdf ■刊行案内 *** 新刊案内 ***(※会員は10%割引でご購入いただけます) 『実務者向け UAVを主体とした複合的な利活用事例集(スペーシャリストの会編)』 (令和5年11月4日刊行) 定価2,420円(税込)//会員価格2,170円(税込) 詳しくは、 https://www.jsurvey.jp/2.htm (遠藤拓郎:日本測量協会) ■編集後記(添付ファイルあり) つくば出向時の同僚が所属するアマチュアの管弦楽団の定期演奏会を観に行きました。 東京港区ARK Hills にある「サントリーホール」。ここは開館当時話題となった「P席」 があります。Pはpodium=指揮者(ラテン語)、すなわち「指揮者の見える席」。かの 同僚に頼んで、P席最前列を取ってもらって当日を迎えました。 ステージにオーケストラが並んで、背面にパイプオルガンがそびえている、その下に ある座席がP席です。通常席で鑑賞していると、オケ前面に陣取る弦楽器群が主旋律を奏 で、管楽器や打楽器はその後ろでどうしても印象薄くなりがちですが、P席からだと管楽 器・打楽器がすぐ間近に見え、彼らの音域の分担やハーモニー、そして、時には楽器の 取り換えや内職!など(ex. フルートとピッコロを持ち換えたり、オーボエがリード交換 をしていたり)、さまざまな動きを観て聴いて楽しむことができます。 音響的にはこの席はNGなんだとは思います。バブル絶頂期の1986年に開館し、P席が 大きな話題を呼びましたが、その後30年以上、この形式の劇場、新たに聞いたことがな いですから。でも、オーケストラを目でも楽しめる、なかなかユニークな会場だと思い ます。開演直前の、私が座った席からの光景を添付に載せました。実は16年前、地元の ホールで、私はこの目線でベートーベン第九の合唱を歌いました。その時の指揮者とサ ントリーホールで再会できたのも不思議なご縁でした。P席さまさまでした。 ものごと、オーソドックスなあたりまえの観点から見るばかりでなく、視点をちょっ と変えると、全く違う光景が見える、異なったハーモニーが聴こえてくる。 そこからまた新しいアイデアが生まれてくるかも知れません。なにより、人生を2倍楽 しむことができましょう。 (編集委員長 : 大山容一(国際航業㈱)) -------------------------------------------------- All Rights Reserved, COPYRIGHT(c) Spatialist Club このメールマガジンを紹介したい方は各自の責任で転送しても結構です。 -------------------------------------------------- | |

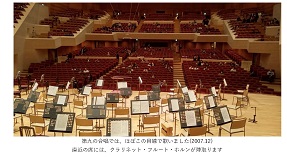
| |
| 戻る | |
| CGIの匠 |